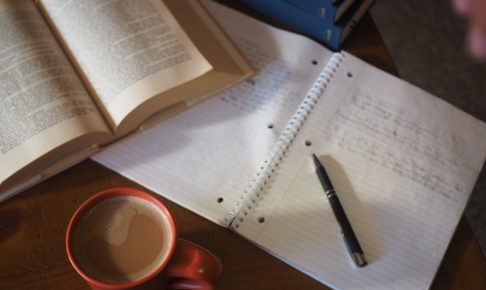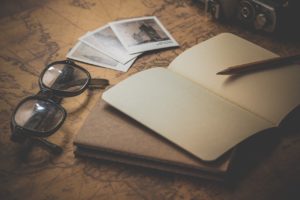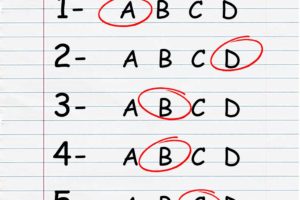生命保険大学課程試験を無事に合格することができました。
取り組み方法やコツなどをご紹介します。

生命保険大学課程試験の受験理由
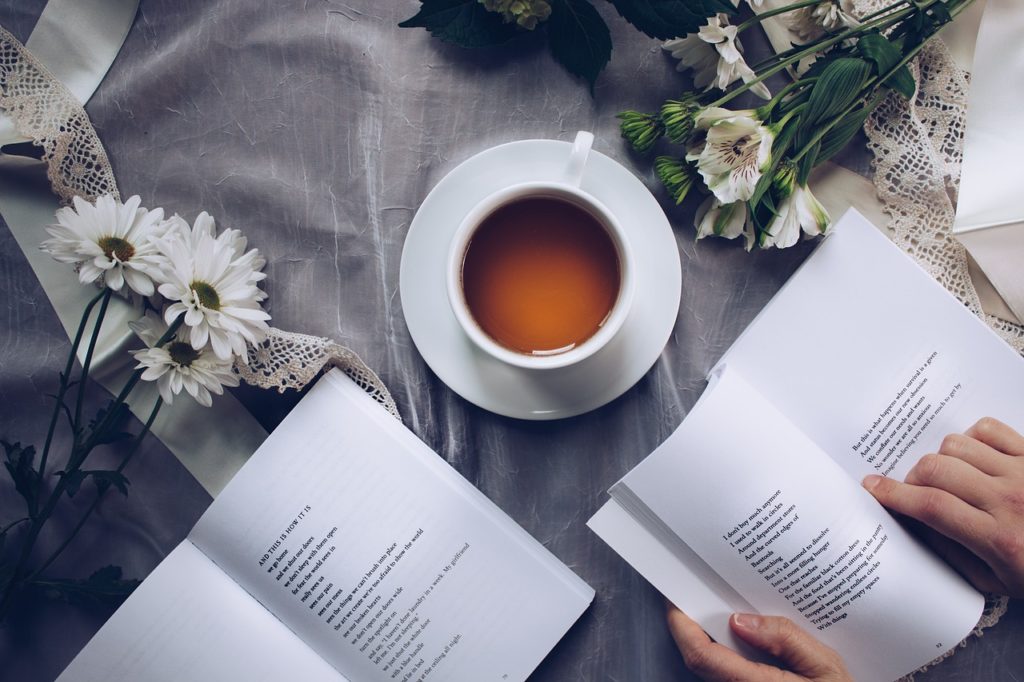
生命保険会社に就職して1年余りが経ち、商品開発に絡む仕事をしていたので、知識量を増やしてより仕事に深みを持たせたいと考えたからです。
応用課程資格試験に合格後、更なる高みを目指して大学課程資格試験にチャレンジすることにしました。
生命保険大学課程試験の基本的な仕組み

生命保険大学課程のカリキュラムは生命保険協会が定めており、計6科目を勉強します。
保険に関係する知識や理解を深めることは当然のこと、「ファイナンシャルプランニング」では、お客様のライフプランに合わせた資産設計の立案方法を学びます。
また、生命保険だけに限らず、損害保険や少額短期保険などの隣接業界の商品や、個人向けや企業向け保険商品の研究も含まれています。
資産運用設計における税金や相続、社会保障についても広く勉強する必要があり、出題範囲は多岐にわたります。
難易度としては、ファイナンシャルプランナー技能検定3級に、実務における専門性を足したレベルです。
試験期間は、一度に6科目全ての試験を受けるわけではなく、2科目ずつ年3回に分けて行われるため、余裕を持って試験に臨めます。
一方で、資格取得まで長くて2年程度かかるため、モチベーションの維持が大切なポイントです。

生命保険大学課程試験に受かるための勉強方法

各科目の合格ラインは60点が目安です。
日々の保険業務を確実にこなしていくことで出題内容に対する理解が深まるため、定常業務が試験の一部だと思っておけば、スムーズに勉強がはかどります。
また、大学課程試験向けの市販本は本屋で取り寄せられるため、手元に一冊持っておくと安心です。
出題傾向をつかむために、できるだけ多くの過去問に触れておくのが望ましいです。
最低でも、過去3回分の過去問を繰り返し解いておくことと並行して、分からない箇所は市販本に戻り、整理しながら進めていくと良いです。
問題文の文章が長いため、一文一文を丁寧に集中して読めるように訓練しておくことも大切です。
文章に違和感を感じたらアンダーラインを引いておき、後から振り返られるようにしておくと理解が深まりやすくなります。
覚えておかなければいけない数字も数多くありますが、図や表にしながらまとめておくと便利ですよ!
生命保険大学課程試験の勉強期間と本番に対する心構え

試験は2科目ずつ年3回開催されるため、年間スケジュールに合わせて計画的に勉強することが大切です。
私は、試験日の3か月より少し前から試験対策に着手しましたが、前半の早い段階でテキストを読み込んで出題範囲の相場観を掴み、過去問を解いていくというスタイルで進めました。
過去問をさかのぼっていくにつれ、項目によっては法改正のタイミングを知ることもでき、問題を解きながら生命保険の歴史も学べるようになります。
余力があれば、数年間分の過去問を手に入れておくと出題傾向が分かるようになり、本番の試験にも安心して臨めるため一石二鳥です。
試験当日は、気持ちを落ち着かせる意味で市販本や過去問集を持参しましたが、試験会場では本を開いて確認することはしませんでした。
試験に集中することを第一に考えられれば、周りの受験者たちが答案用紙に書き込んでいく音も気にならなくなります。
生保協会で大学課程試験の準備をしよう

試験にチャレンジする場合は、生命保険協会が発行するパンフレットやWebサイトなどで要綱をしっかりと確認しましょう。
モチベーションの維持が肝ですが、必ず合格できますので、ぜひ諦めないで頑張って下さい!