「努力が正当に評価されない」と不満を抱いている方は多いでしょう。
その悩みをカリスマブロガーのふろむださんが解決してくれるのが本書、「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」です。
この社会の仕組みは実力ではない
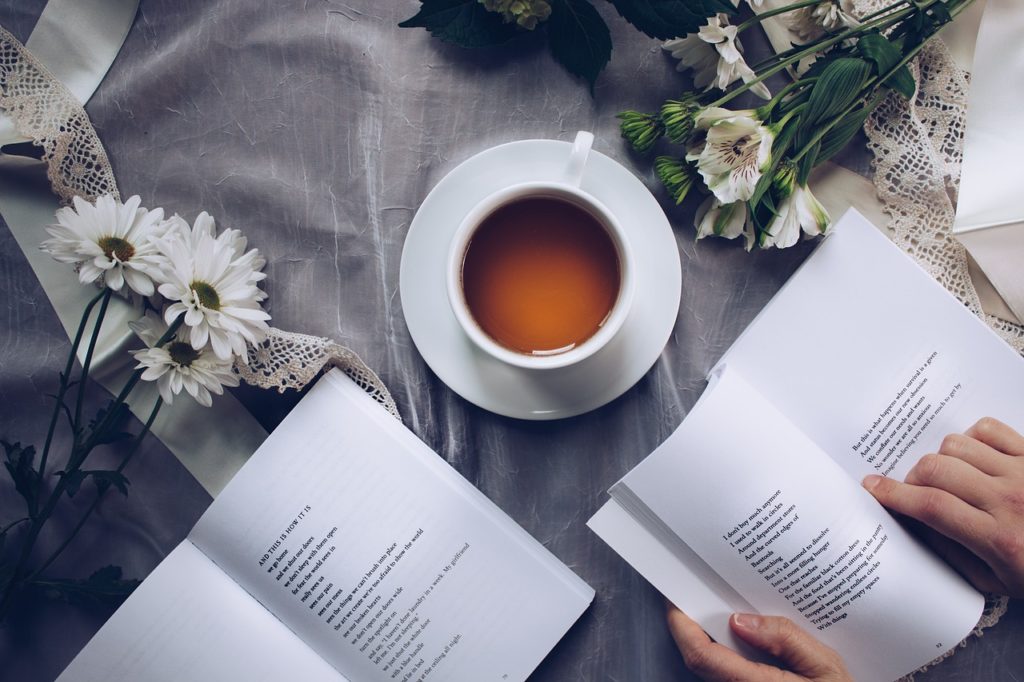
学校では筆記試験という点数化可能な共通の指標によって私たちは評価されてきました。
そして、筆記試験というのは努力によって確実に評価される仕組みであるとも言えます。
そうすると、このような点数至上主義の教育を受けてきた人間は、「この社会というのは、実力が正当に評価されるのだ」と思うようになります。
しかしながら、著者のふろむださんに言わせるとそうではないのです。
組織において、評価をされることを目標にしている方は多いと思いますが、反対に、評価する側というのも基本的には人間です。
したがって、人が人を評価するという行為はどうしても主観的な要素を含んでしまうため、適切に自分の実績をアピールできなければ、自分の望んだ評価を受けることはできなくなってしまいます。
そこで、重要となってくるのが、「勘違いさせる力」です。
勘違いさせる力を持つと、自分の実績は評価されやすい形で解されるようになり、自分のミスは評価に影響を与えないような形で伝わるようになります。
これらのことからわかるのは、社会というのは実力が正当に評価されるフェアなものではなく、いかに自分の都合の良いように物事を相手に理解させるかという「勘違いのさせ合い」が重要となるアンフェアなものなのです。
本書はそういった「本当の社会の姿」というものにも着眼しているため、従来のビジネス書とは違った切り口に感服させられました。
科学的なアプローチに基づく「勘違いさせる力」

「勘違いさせる力」というのが社会生活上重要なものだということはわかりましたが、本書「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」はそれを心理学に基づいた科学的なアプローチによって説明しています。
「勘違い」という言葉を使っているため、小手先のテクニックのような根拠のないものを想像してしまった方もいるかもしれませんが、本書の「勘違いさせる力」というのは心理学の認知バイアス等を根拠に置いているため、評価をされるメカニズムがわかり、結果として様々な場面で応用できるようになっています。
また、「勘違いさせる」と聞くと悪いことのように思えるかもしれませんが、実は社会で活躍するにあたってこの能力は必要なものです。
例えば、画期的なアイデアを思いついたときに、それを会社のプロジェクトとして予算と人員を割り当ててもらうためには、企画書を作りプレゼンをし、上司から承認を得る必要があります。
そのときに、効果的な企画書作りやプレゼンができないと、承認をもらえずにせっかくのアイデアも実現することができなくなってしまいます。
「勘違いさせる力」によってアイデアのメリットを最大化して伝えることができたならば、企画は承認されて実現への道を踏み出すことができたでしょう。
つまり、「勘違いさせる力」というのは決して相手を騙す能力なのでなく、魅力や実績を適切に伝える能力なのです。
上昇意識のあるビジネスマン、努力が正当に評価されないビジネスマンのどちらにもためになる1冊

本書「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」が紹介する能力は、自分のアイデアを実現して社会に貢献した上昇意識のあるビジネスマンにも、日頃努力しているのに正当に評価されずにおいしいところばかり他人に持っていかれてしまうビジネスマンにも、どちらにもためになるものとなっています。
ビジネスマンに求められる能力として、自社の商品への知識や営業力、外国語の能力やITに関する知識など様々なものが挙げられますが、心理学に基づく「勘違いさせる力」も同様にビジネスマンが備えるべき能力と考えていいでしょう。
実力ももちろん伴わなければなりませんが、その実力を適切に評価してもらう「実力」も磨くことを怠ってはなりません。
本書を参考にすることによって、社会人人生をより豊かなものに変えていきましょう。
ふろむださんの「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」で正当な評価をされよう

ふろむださんの紹介する方法は、特別な労力を要しません。
「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」を読んで、人間心理のメカニズムをビジネスに取りいれて正当な評価を受けましょう。



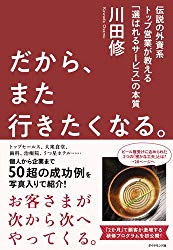
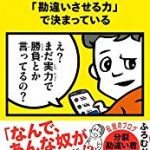
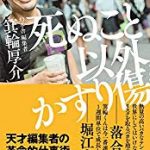


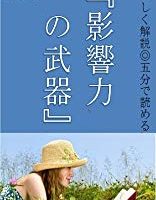
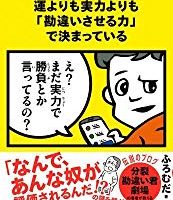

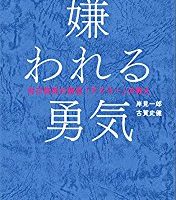


コメントを残す