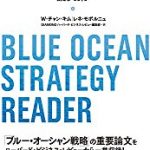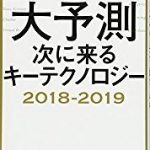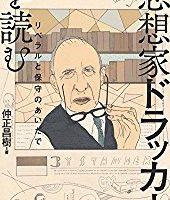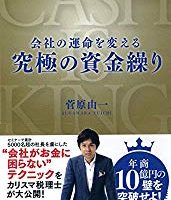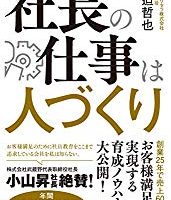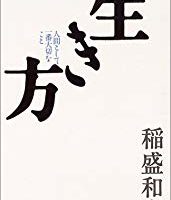ご自身の会社が健全な状態か確認していますか?
中々そのような機会はないかなと思います。第一確認の仕方がわからない。

遠藤功さんの著作である「生きている会社死んでいる会社」は、自分の会社が現在どのような状態かを知ることができます。
そして、会社の見直すべきところもわかる貴重な本です。その概要をご紹介します。
経営コンサルタントの集大成
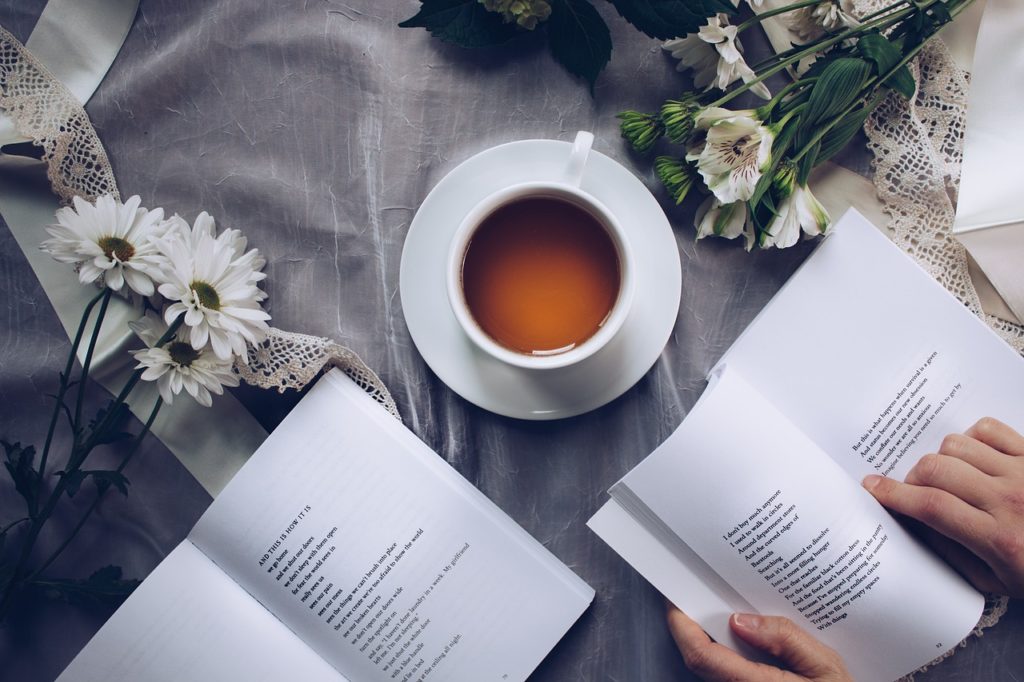
「生きている会社死んでいる会社」を読んだ一言感想は「さすが、経営コンサルタントの意見は違う」でした。
この本を読むきっかけは、会社の経営状態や上司と部下の関係性があまり良くないと感じたからです。
自分の所属する会社が「死んでいる会社」なのではないかと疑い、見直すきっかけになればいいと思いました。
特に、表紙には4つの「新陳代謝」で会社は強くなると書かれています。
この「新陳代謝」の具体的な4つがわからず、興味を持ったというのもきっかけの一つです。
社員一人ひとりの考え方や働き方が変われば、会社の状態は良くなるのではないかと期待しました。
読んでも参考にならないのではないかと思っていたのですが、著者が30年も経営コンサルタントをしていたので、具体的な解決策を読んでみたいと思ったのです。
この本は、働き方を変えるいいきっかけになりました。
「生きている会社死んでいる会社」とは

「遠藤功」著書の「生きている会社死んでいる会社」の概要には、「生きている会社」と呼ばれる有名企業はどのような工夫をしているかが書いてあります。
それらの組織は、見た目の数字や業績よりも組織が生きているということに力を置いているのです。
そういった状態になるには、仕事へのやりがいや組織の団結力を高めなくてはなりません。
その具体的な方法や問題が起きた時の解決方法を導いてくれる本なのです。
また、組織を新陳代謝することも重要と考えています。
具体的に「何をどうすればいいのか」が分かっている会社は「生きている会社」です。
「死んでいる会社」には、新陳代謝をする力や組織の団結力が足りなく、社員のモチベーションが上がらない状態と言えます。
そして、「生きている会社」になるための、「10の基本原則」や若手がのびのびと働ける環境作り、組織が活性化するコツなどを紹介している本です。
「生きている会社死んでいる会社」が伝えたい内容

「生きている会社死んでいる会社」の内容は、会社の「新陳代謝」について体系化しています。
いつまでも「デーワン(1日目)」の活力を保てるかが重要なのです。
「デーワン」の気持ちを保ちながら仕事をすることで、「生きている会社」になりやすいと伝えています。
逆に「デーツー」の会社は「死んでいる会社」になるそうです。
また、事業には寿命があるため、常に「事業・業務・組織・人」を新陳代謝する必要があります。
社員それぞれが問題発見と改善に力を入れる現場力こそが新陳代謝には重要なのです。
そして社員は多過ぎても良くないとも言っています。
「生きている会社」にするためには、具体的には「言える化をして管理の手間を少なくする」「必死のコミュニケーションを務める」などです。
さらに、経営者だけでなく課長や部長などは何をすべきかも書かれています。
見直すべきことが見つかるおすすめの本

「生きている会社死んでいる会社」を読み、ビジネス本でも読みやすいというのが全体的な感想です。
内容的には「デーワン」の気持ちをいつまでも保つことが大切と書いてありましたが、自分や周りの社員にはそれが足りないと反省しました。
また、業務や人の「新陳代謝」の重要性についても納得です。
仕事に慣れてしまうと手抜きになり、社員同士のコミュニケーションもおろそかになっていたと思います。
仕事のメンバーを変えるのではなく、それぞれが今の仕事を見直すだけで「継続的新陳代謝」ができると知りました。
また、経営者は「やらないリスク」よりも「やるリスク」を取るべきだという文章が心に残った内容の一つです。
経営者だけでなく、社員それぞれが挑戦し続ければ、会社の業績や団結力が上がると思います。
この本は具体的な解決方法が書いてあり、今後一つずつ実践してみたいと思える内容でした。
「生きている会社死んでいる会社」を読んでみよう!

「生きている会社死んでいる会社」は経営コンサルタントの集大成と言っていい本でしょう。
実践すべき内容が具体的に書いてあるので、読んで損はありません。
是非、読んでみてください。