トーク力を身につけたいと思い、田中耕比古著「一番伝わる説明の順番」を読みました。
そこには、自分の思いを上手に説明するための極意がわかりやすくまとめられていました。
伝わる順番とは
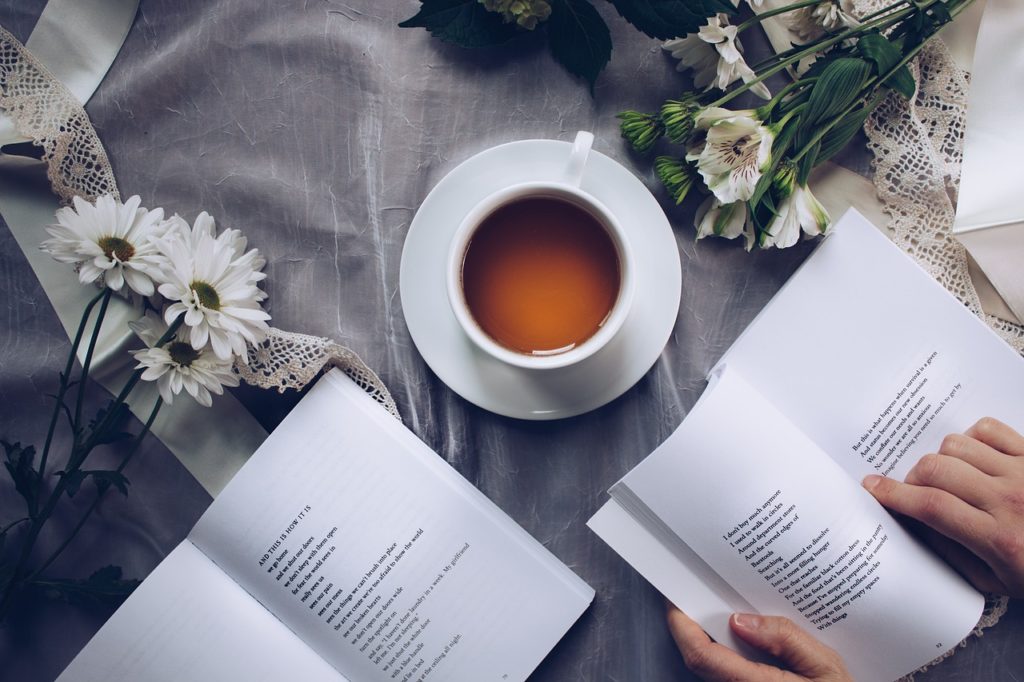
「一番伝わる説明の順番」は、相手に言いたいことが上手く伝わらないという人のために書かれたプレゼンテーション上達法の本です。
コミュニケーションに熟知した戦略コンサルタントによって書かれているため、説明しながら話すというのはどういうことなのか手順を追ってわかりやすく解説されています。
著者によると、説明が上手な人ほど情報を伝える順番を意識するのだそうです。
話す上で大事なことは内容だと思っていた私にとって、この論はとても意外で目からウロコが落ちるようでした。
話す順番を意識するというのは、即ち相手の頭の中を混乱させないように整理しながら情報を伝えるということです。
私自身、情報を伝える時に言いたいことを整理しきれないまま話してしまうことがあります。
自分では一生懸命伝えているつもりなのに何を言いたいのかさっぱりわからないと返されることが多かったのも、相手への配慮が足りなかったせいだと腑に落ちました。
本の中で著者は、話す順番を意識することはそのまま相手の思考の整理に繋がると主張しています。
確かに、私も含めて説明が苦手という人は思いついた順に相手構わずどんどん話してしまう傾向にあるように思います。
これでは、相手が混乱してしまうのも無理はありません。
情報が伝わる順番がバラバラであれば、全体の構成がつかめずに話の本質がわからなくなってしまいます。
説明において必要なのは、相手の頭の中に情報が通る筋道を作りながら順を追って丁寧に説明することなのだそうです。
本書ではその具体的な方法について述べられており、それを実現するために有効なトレーニング法も紹介されています。
テクニックの紹介

前半の章では、説明が下手な理由と間違った話し方について指摘されています。
それを踏まえてわかりやすく説明するための順番が紹介されており、両者を比較しながら読み進められたためすんなり理解することができました。
中盤の章に入ると思考を整理するコツがまとめられており、話す前の自分の頭の中の片付け方と話しながら相手の頭の中を片付けていく方法が紹介されています。
相手の思考を整理するために有効な方法として、フレームワークが挙げられていました。
また、相手の知りたいことや興味があることにフォーカスするのも重要ということです。
確かにどんなに一生懸命説明したとしても、相手の心に響かなければ意味がありません。
その上で話の印象をより強くするためのコツについても書かれていたので、機会があったら私も使ってみたいと思いました。
最後の章では、日常的に取り入れられる説明力を向上させるための思考の習慣やトレーニング法が展開されていきます。
トレーニング法としては二つのやり方が挙げられており、一つは説明を要約するためのサマライズトレーニング、もう一つは相手が理解しやすくなるように具体化するクリスタライズトレーニングです。
また、話題の飛躍を防ぐために本質を見極めることの必要性についても説かれています。
その他、明確に本質を伝えるために思い切って話の一部を端折る方法についても言及されていました。
所感

これまでの私の説明のやり方は、自分が大事だと思う部分を強調して繰り返し何度も訴えるという強引なものでした。
とにかく内容を伝えることに必死で、それが相手にスムーズに伝わるかどうかについては考えていなかったように思います。
これでは大事なことが伝わる訳がありません。
実際に、自分では伝えたつもりが相手に全く伝わっていなくてトラブルになったことも多々あります。
この本を読んで、今までの自分の説明がいかに間違っていたのかということを知ることが出来ました。
適当な順番で話をしないということや行き当たりばったりの思いつきで話をしないということを肝に銘じた次第です。
この本で知り得た知識は、仕事におけるプレゼンテーションやミーティングの席で活用できるのはもちろんのこと、日常生活の何気ない会話にも応用できそうです。
そのためにも、この本に書かれていたトレーニング法で思考の整理術を会得して頭の回転を良くしたいと思います。
また、会話というのは相手があってのものなので向こうの思考についても考慮しながら思いやりをもって会話をすることを心がけたいです。
説明が上手になるために

この本を読むことで、長年悩んできた説明が下手というコンプレックスが解消できそうです。
日常生活で実践しながら身につけていこうと思っています。
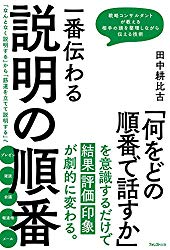

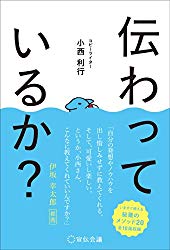
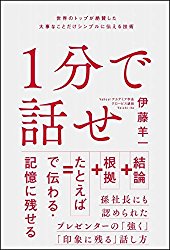

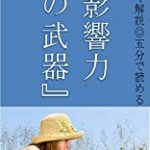
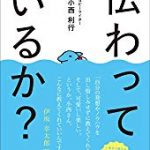
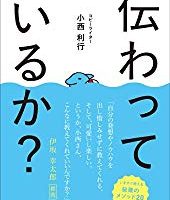
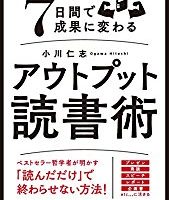


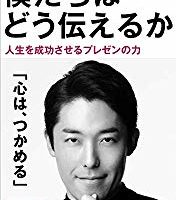

コメントを残す