アウトプットが苦手…と感じる人は多いのではないでしょうか。何を隠そう、私もその一人でした。しかし、この本を読めばそれを克服できるのです。
アウトプットはわくわくする!
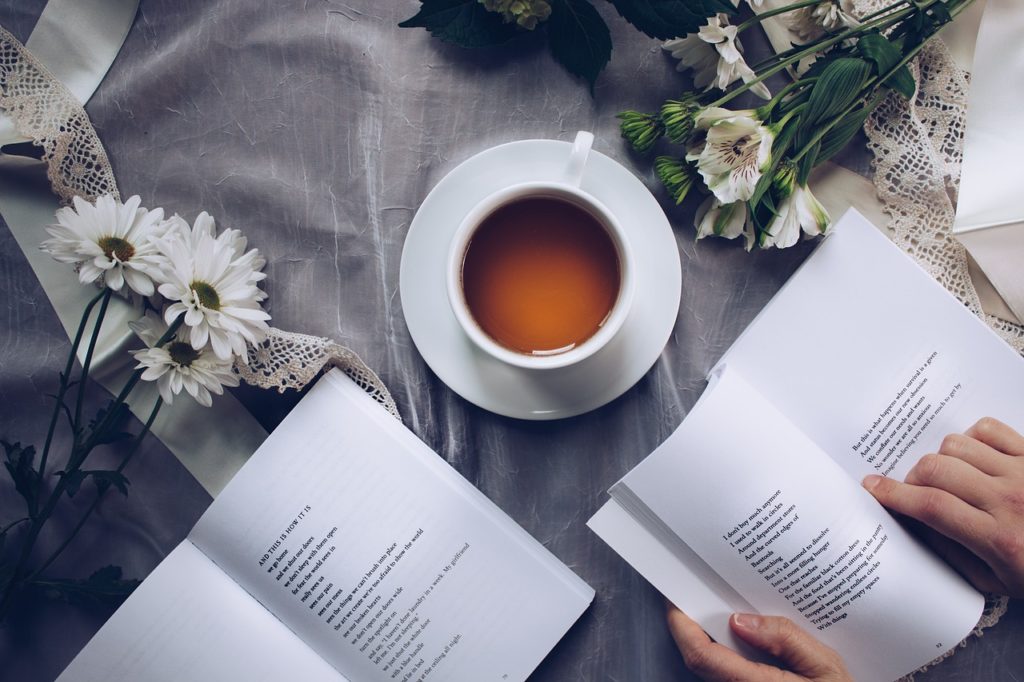
一言で感想を言うと、「本当に読んでよかった!この本に出会えてとても有益だった!」ということです。
実際に胸がドキドキして興奮を覚えました。面白くてタメになると感じ、実際に実行していけそうだという実感と勇気を得ることもできました。
大切なのは…インプットよりアウトプット

この本はアウトプットをすることによる様々な目覚ましく良い効果について、実に80個ものアイデアや提案がされています。
筆者の体験や考察を交えた非常にわかりやすい文章で、長いぺージ数ではありますが楽しく読むことができます。
この本の中で筆者は繰り返し、重要なのはインプットの量ではなく、アウトプットの量だと説いています。
なぜなら、いくらインプットしてもアウトプットを行わない限り、記憶として定着しないからです。
多くの人は読書や勉強会などで情報を「わかったつもり」になっているだけで、実際には知識として活用できておらず、何の役にも立たないいわば自己満足なのだといいます。
これには自身にも思い当たる節が大きく、耳が痛い話でした。
筆者はメルマガを13年間毎日発行し、フェイスブックとYouTubeの更新も毎日それぞれ8年と5年、毎日3時間以上の執筆を11年、10年連続で年に2、3冊の本を出版し、新作のセミナーは毎月2回9年連続で続けているとのことで、実に恐ろしいほどの量のアウトプットをしています。
私がそれよりもっと驚いたのは、それだけのアウトプットをしておきながら毎日7時間の睡眠を確保し、遊びやリラックスするプライベートモードも大変充実していたことです。
本をたとえ100冊読んだとしても、アウトプットをしない限り現実の世界は何一つ変わらないのです。
アウトプットには大きく分けて「書く」「話す」「行動する」の3つがあげられます。
私はアウトプットというイメージで、「書く」ことを大きく考えていたのですが、人と話したり、笑顔を作ることもアウトプットなのだそうです。
具体的な方法も丁寧に書かれていて大変参考になります。
こうすればもっと生産的なアウトプット

特に私が感嘆したのは、アイデアの出し方でした。
1つのアイデアにつき、できるだけたくさんのアイデアをアナログで紙に書き、それをカテゴリーで分類して、さらに考えて再分類をしてからデジタルメディアでまとめるという方法です。
抽象化が得意なアナログと具象化が得意なデジタルは用途に応じて使い分けることが最も大事なことです。
今までずっと、上手くアイデアをまとめる効果的な方法を模索していたので、早速取り入れることにしました。
もうひとつは、文章を書く際には構成を決めてから書くという箇所です。
構成はいわば文章の設計図で、これがしっかりしていると格段にやりやすいことがわかりました。
当たり前のことかもしれませんが、再度理解を深めました。
他にも企画書の書き方、人にものを教える、時間を管理する、など多数の実践的な内容がありました。
アウトプット力を高めるトレーニング法として、日記や読書感想文を書くことがあげられています。
特に日記を書くことによって、自己洞察力や内省能力、ストレス耐性が高まるとされており、利点がとても大きいため私も時を移さず実行することにしました。
ストレス耐性など、一見アウトプットに無関係なイメージがありましたが、意外な効用も期待されるとは…驚きました。
また、時折挿入されるイラストもシンプルで可愛らしく効果的です。もともと読みやすい文章ですが、説明のイラストでより理解しやすくなっています。
難しいことをわかりやすい文章で表現するのは高い技術が必要です。
あなたも今日からアウトプットを始めよう

アウトプットは非常に大きなメリットを持ち、また楽しい作業だということがよく理解できました。
ぜひアウトプットを積極的に行い、人生を豊かにしていきたいですね!
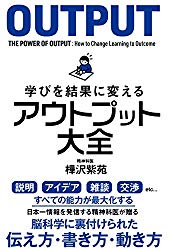

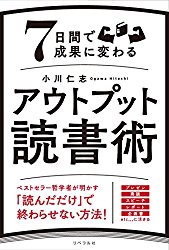
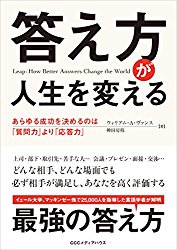
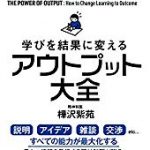
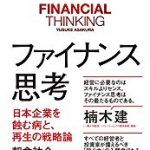

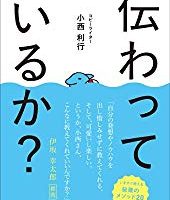
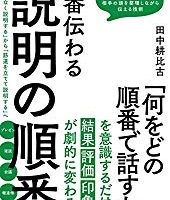
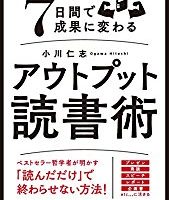


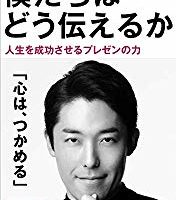

コメントを残す