想像できないほど計算処理が速く大容量の情報を蓄え、瞬時に通信で世界中とつながる。
そんな「AI」と共に生きる時代の、中学生からビジネスパーソンまでの指南書「みんなでつくるAI時代」は必携の一冊です。
AIに職を奪われる、と怯えますか?
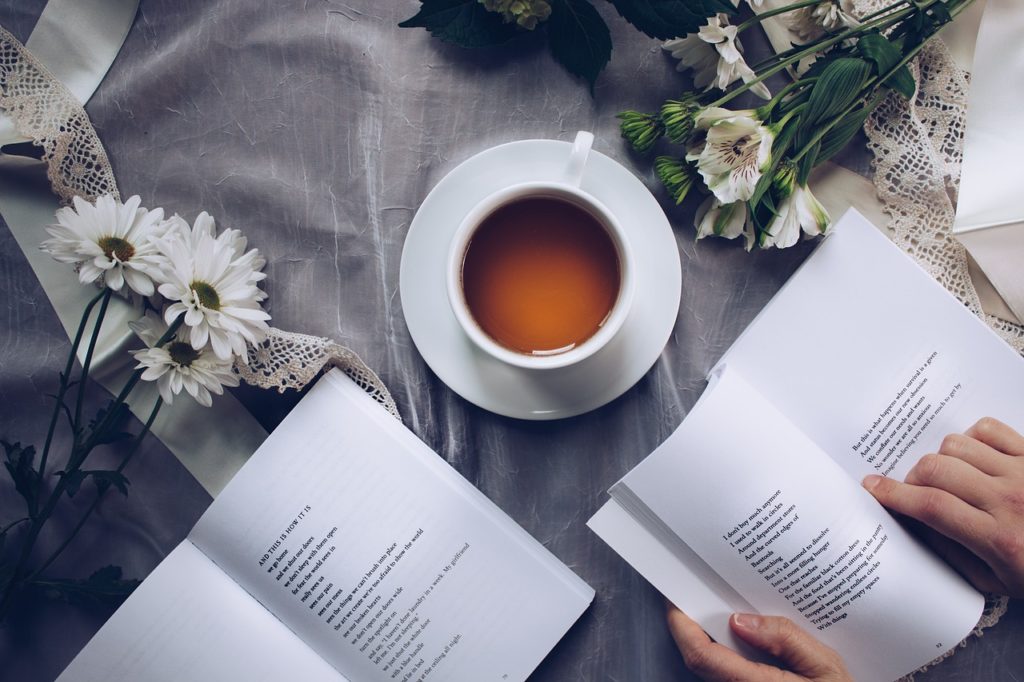
ビジネスパーソンにとっては、すでに金融から農作物の管理まで、いかに幅広くAIが実装され得るか知らない人はいないでしょう。
しかしそうなる一方で、かつてないスピードで既存の仕事が淘汰される時代になっている、ということも事実として受け入れざるを得ません。
多くの人間を必要としていた仕事が、賢くなった機械や計算機に取って代わられるというようなマイナスイメージに引きずられ、いたずらに恐れたり警戒したりするよりも、前向きな未来を考える方が現実的なのは言うまでもないでしょう。
具体的には、社会のニーズと科学技術をつなぐ仕事や、物事の本質を分析する仕事がこれから顕在化します。
このことは、今までの理系・文系といった分類ではおさまらない、新たな教養ジャンルが登場することを意味します。
STEAMは、科学(Science)技術(Technology)工学(Engineering)芸術(Art)数学(Mathematics)の頭文字をとった言葉です。
一旦世界に目を向けると、このSTEAMの5分野を併せ持つことが重要視される価値観と、その教育が始まっているのです。
著者・伊藤恵理について

第一作目『空の旅を科学する-人工知能がひらく!?21世紀の「航空管制」』(河出書房新社)では、みずみずしい若き駆け出し研究者の視点でフランスやアメリカで得た知見がタイムリーに披露されました。
しかしそこには書き切れなかった、ある大切な秘訣を、本書「みんなでつくるAI時代」に込めたという著者・伊藤恵理は1980年生まれで、現在、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所主幹研究員です。
世界の空には約6,000機を超える飛行機と共に、およそ100万人が瞬間的に空を飛んでおり、航空管制はまさにその命綱。
安全で効率的に、なおかつ環境への負荷を低減しながら空の交通整理をするということは、AI時代の社会に役立つシステムをどのように企画・設計し実用化するか、という課題がまさに集結したような仕事です。
さらに、その国際基準をつくるということは、複雑な交渉や技術革新の積み重ねを要します。
そんな経験で磨かれた著者の、知的でタフでありながら、細やかな目配りやユーモアも忘れない柔軟なスタイルが、本書でも遺憾なく発揮されています。
STEAMというキーワード

本書の魅力は、まず、ビジネスパーソンが知っておくべき、世界最高峰の専門家たちによる鮮度の高いAI事情が披露されていることです。
スマートシティの設計や、NASAの技術が社会につなげられていく様子、さらには実際にビッグデータで交通渋滞を解消するなど、インパクトのある具体的事例が、テンポのよい筆致と共に数多く紹介されています。
それらを追ってゆくうちに、一見、専門的なジャンルの事例かと思えたものが、実は普遍性と応用の可能性に満ちたものであることを、知的興奮と共に実感できます。
そして、著者が最も伝えたいSTEAMというキーワード。
このことによって拡張される人々の可能性とは、文系ならではの科学リテラシーへの理解や洞察力を活かすこと、あるいはその反対に、理系だからこその論理的思考法を意外な切り口で応用することなど、まさに目から鱗が落ちるようなヒントが満載です。
これからの時代を生きる上で、また、そんな時代を生き抜いてゆく人材の教育において、必要とされる視点であることが痛感できます。
こんなヒントやAIを取り巻く知識も満載

技術と社会の架け橋となるべき専門性とは、つまるところ、人間について考察を深め追及してゆくことに他なりません。
実際に、STEAMのそれぞれ5つの分野の専門家たちによって「インスピレーションを教育することはできるか?」「科学的思考を社会問題の解決にどう役立てるか?」「知識が多いと幸せになれるのか?」といった問いがどう取り組まれているのか、非常に深いヒントが隠されています。
また、本書の特徴として、現在に至るAIをめぐる議論の歴史や出来事の背景についても詳しく記載されています。
たとえば「AI時代、人類の未来は明るいのか?」というダイレクトな議論について、実際に2015年秋に行われたアメリカのムンク財団による熱いディベート大会の様子が報告されています。
またスリリングな「ペトロフ事件」についても考察されており、著者のジャーナリスティックな側面もうかがえます。
AIにできないことを正しく知るために

AIは「美しい」を理解するでしょうか。
実は人間が分析し言語化・数値化できる限りの情報と事例を、AIは反映するだけなのです。
時代の主語は、AIではなく、どこまでいっても人間なのです。
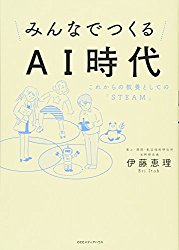

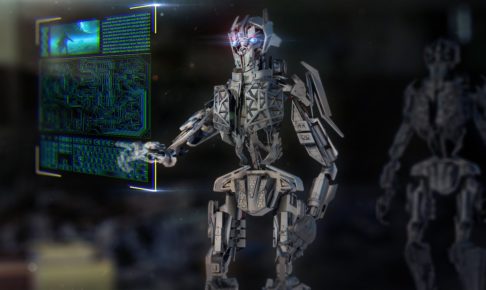
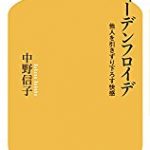
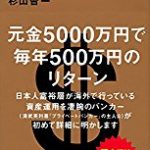
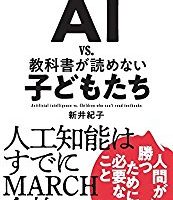
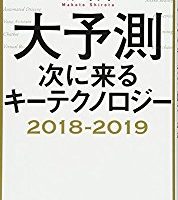
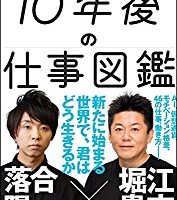
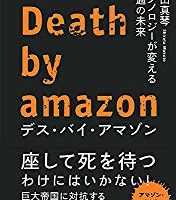
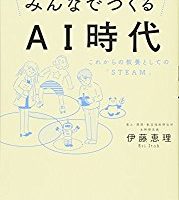
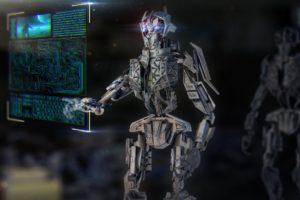

コメントを残す