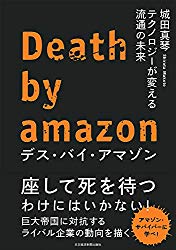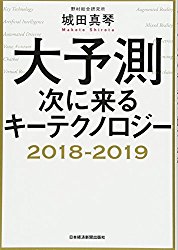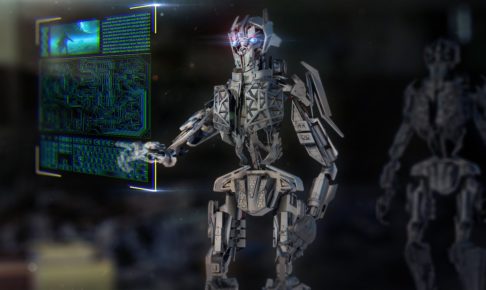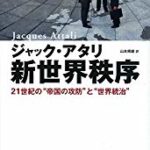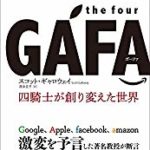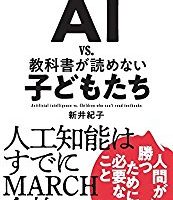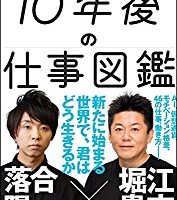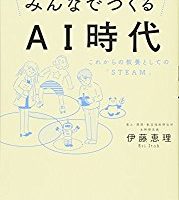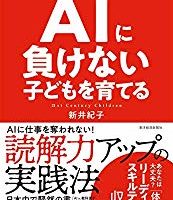「デス・バイ・アマゾン」は、巨大企業アマゾンの台頭によって市場競争で何が起きているのかを分析した一冊です。
著者の城田真琴さんは、未来予測の研究者として活躍している第一人者で、世界視野で最先端のテクノロジーついて研究されている方です。
多様な戦略性への驚き
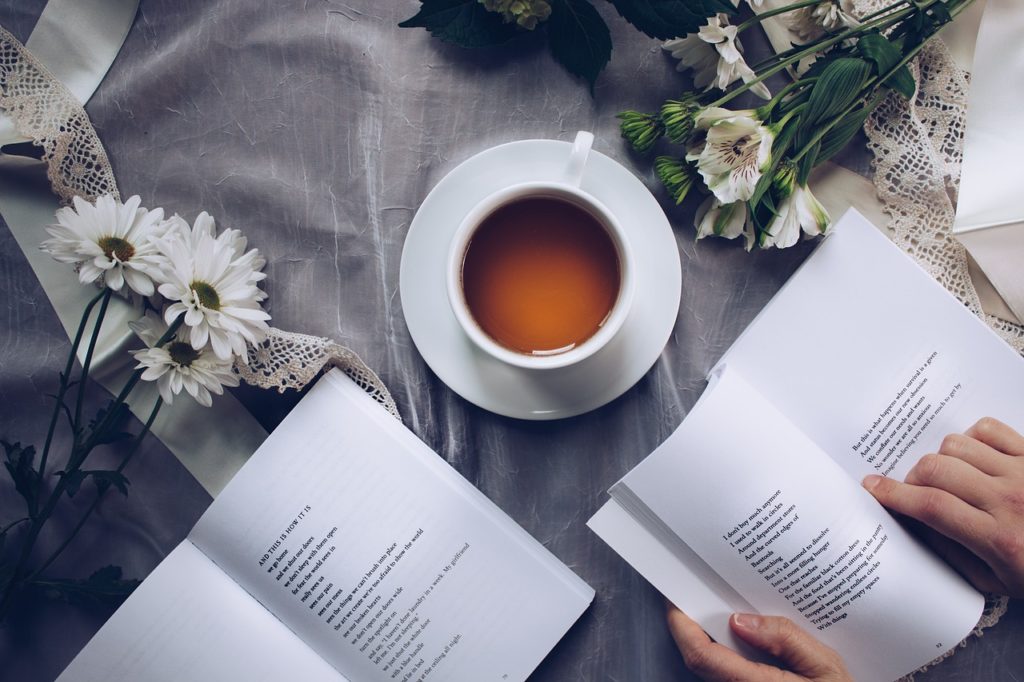
アマゾン社の台頭によって市場での競争力を弱めていく企業を「デス・バイ・アマゾン」と表現しています。
アマゾンを中心に取り上げられているのはもちろんですが、競争で窮地に陥ったライバル企業もさまざまな戦略で生き残りをはかっていることも記載されていてとても興味深い一冊になっています。
スペシャリストが斬る、市場の激化

アマゾンが消費者戦略に長けていることはよく知られています。
本書でも取り上げられているように、どこにいてもネットで手軽に買い物ができるシステムの構築に始まり、AIを利用した消費者の消費動向調査などを通じて顧客により的確な情報を提供するサービスなど、流通・小売の分野での実力は非常に高いものです。
最近でも、「アマゾン・ゴー」の市場進出など、その勢いはとどまるところを知りません。
本書は、そんなアマゾンの躍進に押され、大きな打撃を受けている企業とその「生き残り戦略」にスポットを当てています。
これは、流通や小売、マーケティング産業に携わる企業や経営者はもちろん、全ての人々の消費行動に関わる動きです。
ビジネスに関わる人にとっては、ぜひとも押さえておきたいところでしょう。
産業技術の最先端を知り尽くした著者の城田真琴氏が、アマゾンの躍進とそれに抵抗する企業の動きに鋭く切り込みます。
アマゾンの驚き、ライバル企業の驚き

アマゾンの躍進で業績の悪化が危惧されるアメリカ企業の状況は、「アマゾン恐怖銘柄指数」という言葉で表現されています。
アマゾンが始動したさまざまなサービスの多くは、どれも斬新で先進的な試みばかりでした。
その一例が、レジのない無人店舗「アマゾン・ゴー」です。
オンライン事業でありながらリアルの店舗を展開し、それを無人で運営するという試みは大きなインパクトをもたらしました。
日本では、ユニクロなどの巨大企業もアマゾンの戦略に危機感を覚えているといいます。
事実、どこにいても手軽に買い物が楽しめるアマゾンのサービスが他の小売・流通企業に与える影響は小さくないでしょう。
しかし、ライバル企業たちも黙って見守っているわけではありません。ニトリやZARA、楽天などの日本企業も「デス・バイ・アマゾン」を免れるためのさまざまな戦略をとっています。
たとえばZARAは、専用アプリ等を利用した先駆的なデジタルサービスを展開し、小売業の分野で差をつけようとしています。
楽天は、ドローンによる配送サービスを先行的に実施し、流通分野での生き残りを試みています。
他にもアマゾンに「殺されない」ための戦略は多種多様で、ライバル企業たちの努力が覗えます。
本書はアマゾンの技術的な先進性を前提としていますが、単純にアマゾンを礼賛しているわけではありません。
むしろ、「デス・バイ・アマゾン」を警戒するライバル企業の動向に注目することで、厳しい市場競争で生き残るためのヒントを提示しています。

技術と経済が紡ぐ未来

アマゾン躍進の陰に隠れたライバル企業の戦略は、非常に興味深いところでした。
技術の発展が経営戦略のカギを握っていることは確かであり本書のサブタイトルも「テクノロジーが変える流通の未来」とされていますが、本書で中心に分析されているのは技術それ自体の意義というより、むしろいかにして顧客に働きかけるかという戦略性なので、ビジネスに関心のある人にとってはいずれも興味深い話題だと思います。
また、アメリカに限らず日本の企業もアマゾンの影響を危惧しており、さまざまな戦略を練っています。
グローバル化がますます進展する現代において、「デス・バイ・アマゾン」は対岸の火事ではないのでしょう。
未来のビジネス分析のヒントに

経営者やビジネスの現場に立つ人にとってはもちろん、今後数十年のビジネスの未来を考えるうえで必読の良書です。