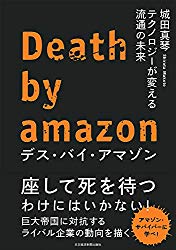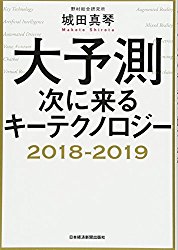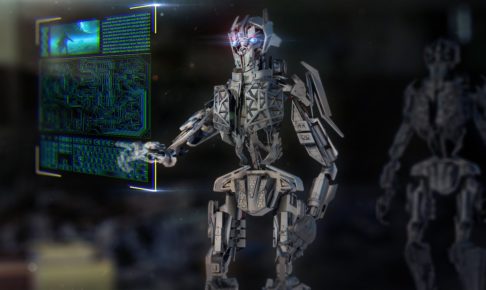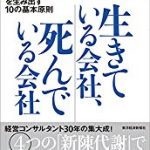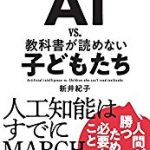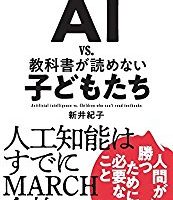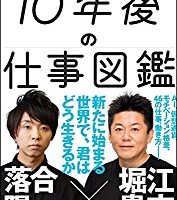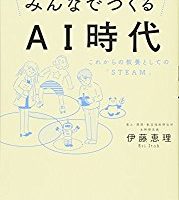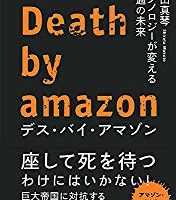未来予測の研究者として活躍している城田真琴さんの経歴とその考えを深掘りしていきます。
日本をけん引する、クラウド、M2M、IoTなどの第一人者です。

これまでの経歴
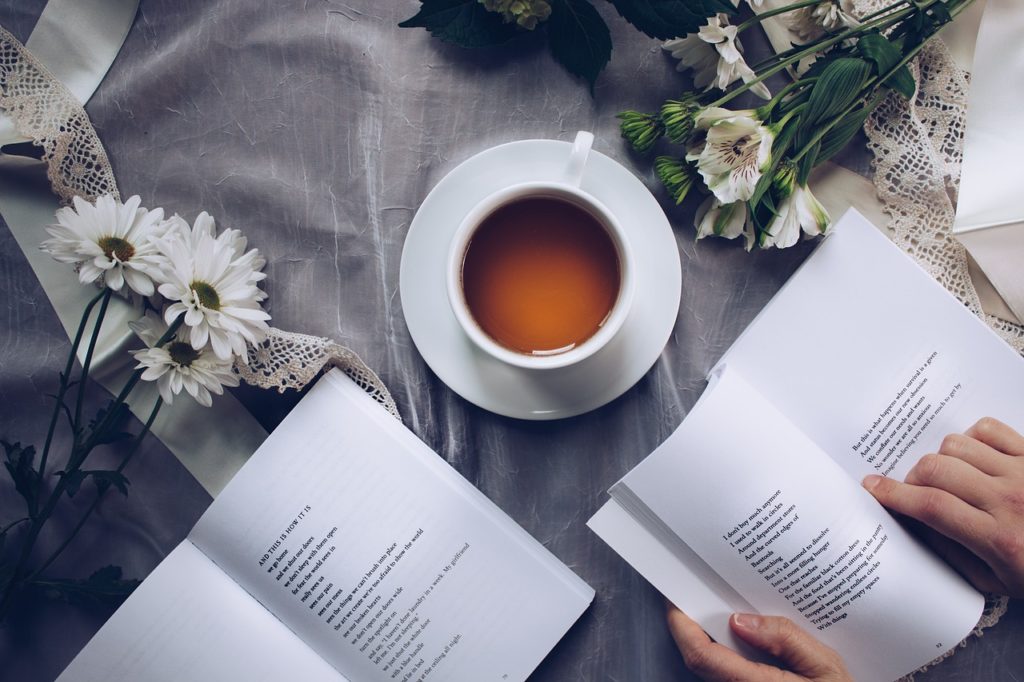
城田真琴氏は1971年に北海道の旭川市で生まれました。
1990年に北海道大学に入学して、1994年に同大学の工学部電子工学科を卒業してからは大手メーカーのシステムコンサルティング部門で勤務しました。
2001年からは現職の野村総合研究所イノベーション開発部に勤めています。
野村総合研究所に入社して以来、ずっと先端技術の調査・発掘をし続けていました。
そして、経済産業省の「IT融合フォーラム」のパーソナルデータワーキンググループ委員を歴任したり、総務省の「スマート・クラウド研究会」の技術委員を2009年から2010年務めるなど活動内容は幅広いです。
ITアナリストとして最先端のテクノロジーがどのようなものなのかを調査したり、企業の戦略を分析したり、IT業界の未来予測などをメインに企業にアドバイスをしています。
担当領域はクラウド、M2M、IoTなどです。
また、これまでに数多くの著書を発売しています。
たとえば、『大予測 次に来るキーテクノロジー2018-2019』、『ビッグデータの衝撃』、『クラウドの衝撃』、『今さら聞けないクラウドの常識・非常識』などです。
特に『クラウドの衝撃』はベストセラーにもなり、最近発売した『FinTechの衝撃』は読者に大きな衝撃を与えました。
城田真琴氏はここ数年ずっとFintechに関する研究を行っていて、『FinTechの衝撃』の中で「マーケットプレイス・レンディング」「ロボアドバイザー」「モバイル決済・送金」などのFinTechサービスを詳しく説明しています。
この分野に関する第一人者といっても過言ではありません。
さらに、テレビにも数多く出演しています。
これまでにNHKの「ITホワイトボックス」、テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」、BSフジの「プライムニュース」などに出演経験があります。
他にも、新聞や雑誌などにも雑文を多く投稿しているなど執筆活動にも精力的です。
城田真琴氏の考え

城田真琴氏は日本企業や日本人ビジネスマンにFintechサービスに注力するように広く主張していることでも有名ですが、これはとても共感できることです。
著者の考えでは2008年から2009年に起こったリーマンショックによってアメリカの大手金融機関の信用が非常に低迷しましたが、日本ではそうした事態が起こっているとは見ていません。
未だに日本の金融機関に対する信用度は高い状況にあるからこそ、日本の金融機関によるFinTechサービスが大きく受け入れられる可能性があると考えています。
ただし、日本の金融機関をはじめとして多くの国内企業は新しいことにチャレンジするときにリスクを考えてなかなか踏み切れないということで批判もしています。
私自身も城田真琴氏のこの考えに賛成でメガバンクが積極的にFintechサービスを導入していけば、その規模がどんどん拡大して経済のますますの活性化につながるのにもったいないと感じています。

また、城田真琴氏は日本企業の閉鎖的性格も鋭く批判しています。
日本企業の多くが新卒採用をメインにしていて、社内にプロパー社員ばかりだけで構成する傾向があることを指摘しています。
この点についても、中途採用も積極的に行うことでいろいろな経験を持った人材を獲得した方が新しい息吹を与えて良いと私も思いました。
さらに、昨今のブロックチェーン問題についても同様に考えを発信しています。
仮想通貨の登場によってブロックチェーンが注目され始めていろいろな分野でその技術が採用されていますが、The DAO事件をはじめとしたブロックチェーンに関する問題が生じました。
これはハッカーによって引き起こされた事件ですが、ハッカー対策のソリューションが新しくどんどん生まれたことでブロックチェーン問題も解決されている状況です。
日本企業はハッカーのリスクを恐れてまだ二の足を踏む企業が多い中、城田真琴氏は金融機関における送金と入金にブロックチェーンが世界的に導入されていくだろうと予測しています。
この予測は今後の金融システムを考えると非常に正しいものだと思います。
城田真琴氏のこれまでの経歴を見てみると非常に堅実な人生を送ってきたと思われますが、その主張は決して当たり障りのないことではなく、非常に刺激に満ちたものになっています。
日本のビジネスについて考えるときに必ず欧米などの海外ではどのような状況なのかという世界的な視野に立って考察しているのも魅力的でしょう。
日本がグローバル化の波にさらされて久しいですが、そのような状況の中にあるからこそ海外の視野を持つことはとても大切だという同氏の考えにも共感できます。
このように、著者はまだまだ新しい分野に対してその先見の明をいろいろな著書で披露しています。
特に、IT業界に関する最先端の技術を知りたいと思っている人には絶対に知っておいてほしい人物でしょう。